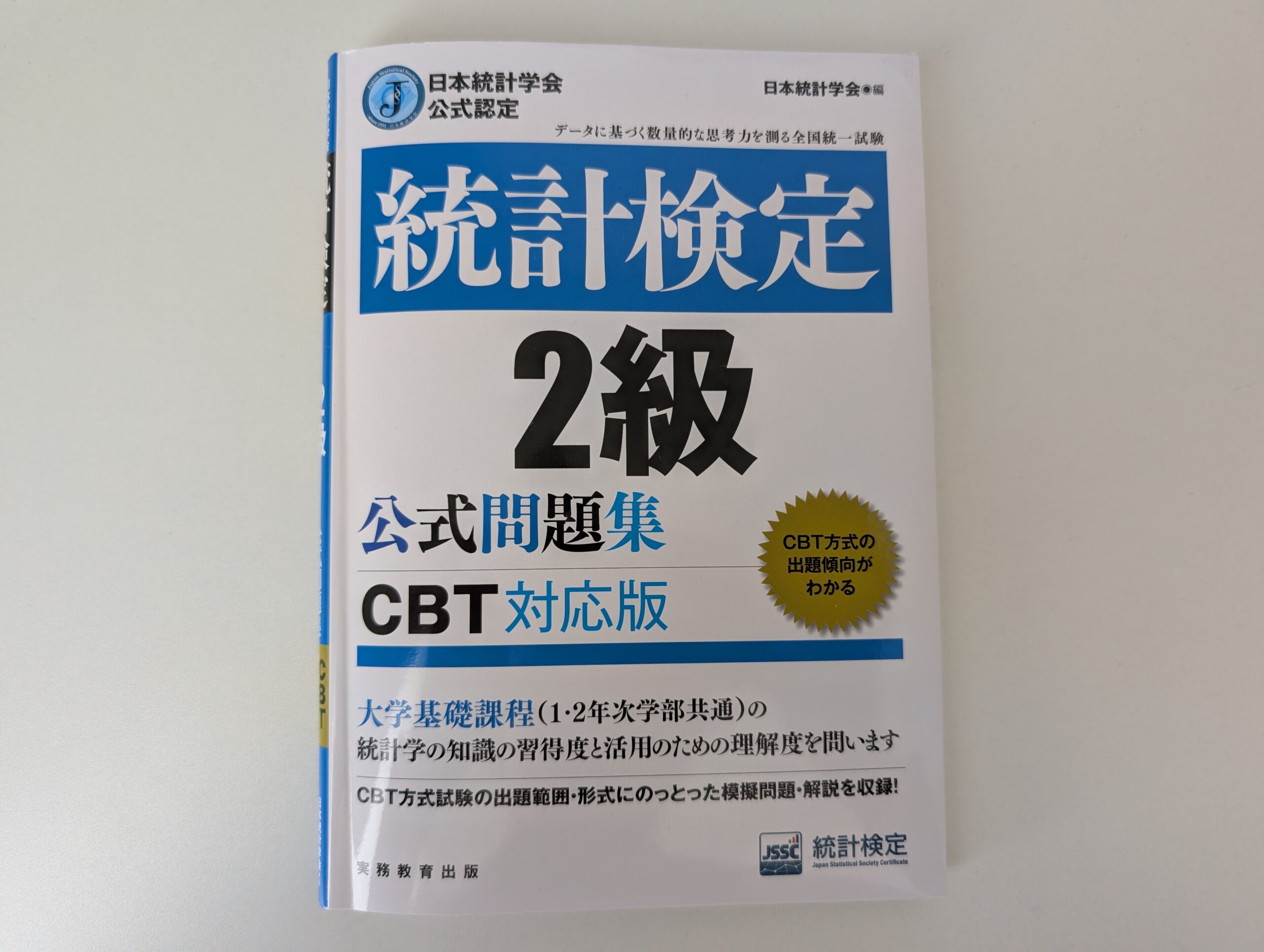俺はこの4月に統計検定2級に合格した。そんなに自慢できるような点数でもないギリギリの点数だったし、統計検定2級自体、多くの人が受験し、合格している人もいる。
誰かの役に立つかもしれないので、俺が統計検定2級に合格するまでの道のりを記しておこうと思う。
俺の学力
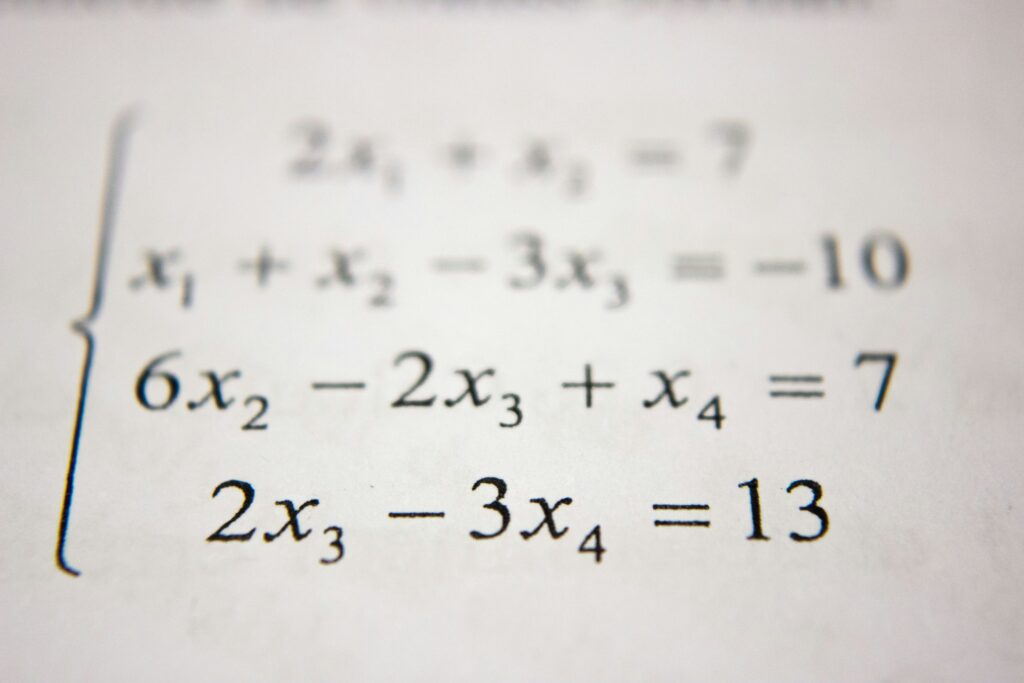
統計検定は知識としては主に数学の知識や計算が必要になる。そのため、参考として俺の数学の学力についてはじめに提示しておこう(記憶が曖昧なところある)。
- 受験生の時の模試の数学の偏差値:60〜65(調子いい時は60台後半の時も)
- 高校数学の履修状況:数学Ⅲまで(俺が学生の時は数学Cは存在しない)
- センター試験の数学の点数:180〜190くらい
学力に関しては2浪しているが、ひとまず統計検定2級を勉強するのに必要な基礎学力は身についていたと思う。実際に統計検定2級の勉強をしてみて、少なくとも高校数学の確率の分野の知識は必要であると思う。また、計算式や途中計算で積分が出てきたり、Σが出てくるので、基礎レベルでも良いので高校数学で学んでおく必要があると感じた。
ここら辺が微妙な人や高校の時に履修していなかった人は、統計検定の問題をやりつつ、ネットやYouTubeで高校数学の基礎も学ぶ必要があると思う。必要となる分野としては、確率、数列、積分あたりだろう。難しい問題を解けるようになるまで勉強する必要はない。これらの分野の基本的な用語や計算方法、理解はしておくべきだ。それでもやはり、初めて聞く用語や知識はどうしても出てくるので、それはその都度覚えていく。
では、実際に俺がどのような勉強をしたのかを紹介していこうと思う。
最初は過去問テキストをやってみた
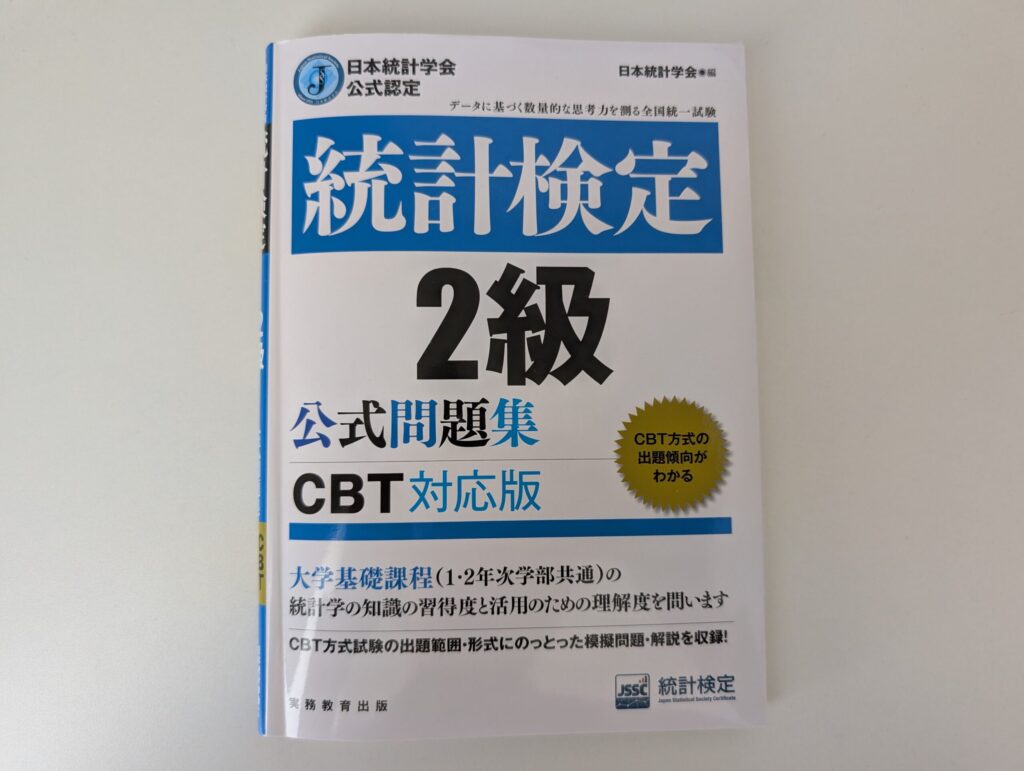
まずやったことは、統計検定の過去問テキストを購入して、解いてみた。まずは、敵を知ることが重要だ。どんな敵が出てくるのかわからなければ、どんな対策をすれば良いかわからない。
俺は過去問を時期的には2024年の7月くらいに購入したと思う。ただし、この時はあまり本格的に試験のための勉強はしておらず、趣味の一つになればいいかなくらいのモチベーションでやっていた。本格的に試験勉強を始めたのは3月からだ。
実際に解いてみると、統計検定の勉強をしていなくても、高校数学の知識だけで解ける問題もあることがわかった。逆に、高校数学では習わないような統計学の知識を使う問題は過去問テキストの解説をみても何をしているのかわからないものが多かった。
ひとまず、この段階で解けた問題や高校数学範囲は放置することにした。
統計学の知識が必要な問題に関しては、解説を見てもわからなかったので、ネットでひたすら調べながら、知識を吸収していくことにした。するとなんと、統計検定の過去問テキストの問題の解説をしてくれているnoteを発見。テキストの解説よりわかりやすかったので、その解説を見ながら理解していく方針にした。
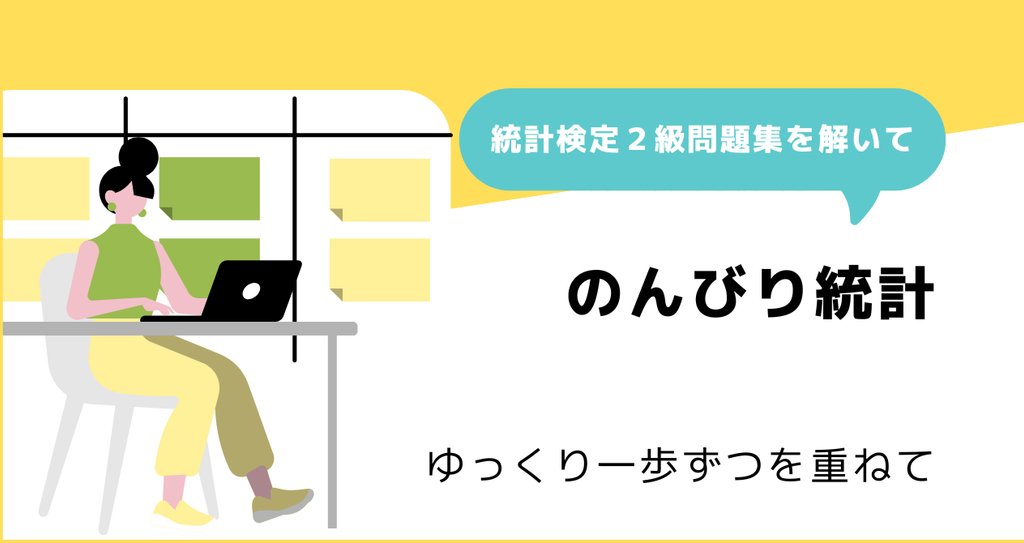
このやり方でとりあえず、テキストを3周ほど繰り返し解いてみた。
最終的に俺が使った過去問テキストはCBT対応版の1冊だけだが、3冊くらい年度別で出版されているので、演習量を増やしたければ、2冊目・3冊目をやっていくといいと思う。
3周やっても解けない問題や理解が曖昧な問題があったので、さらなる対策を考えることにした。
教科書を買ってみた
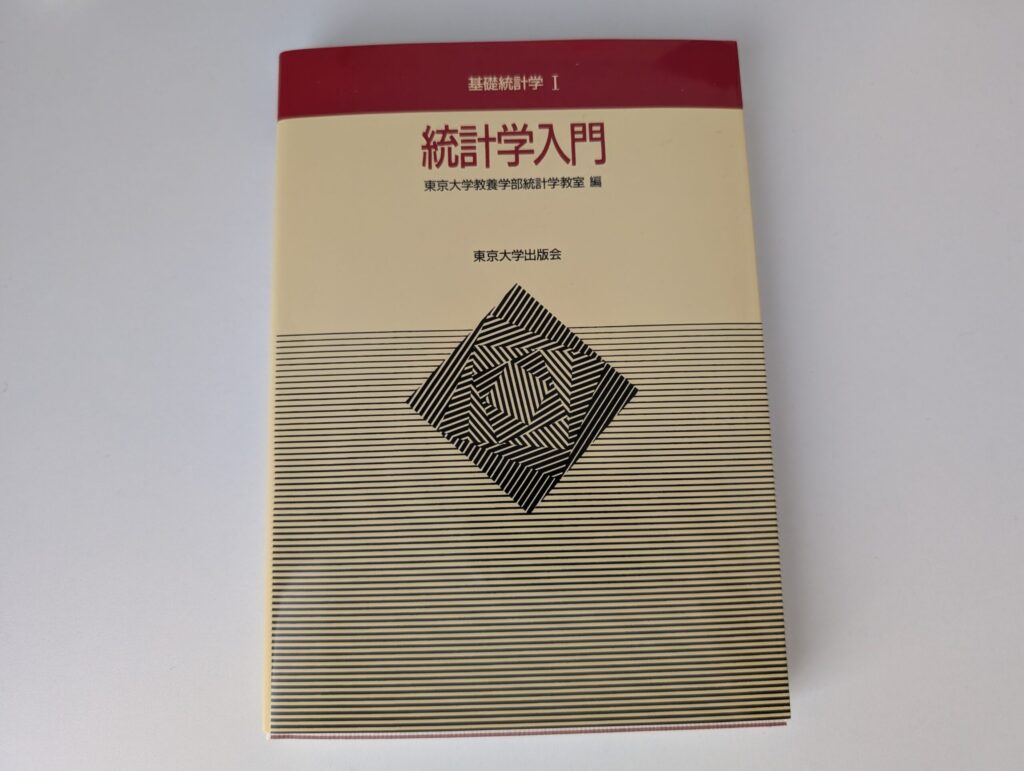
問題を繰り返し解いていく中で、解けるようにはなっているが、理解が曖昧な部分やそもそも何回解いても間違える問題があった。そこで、より理解を深めようと思い、統計学の教科書(統計学入門)を購入してみた。
結論から言うと、この教科書はほぼ使わなかった。
原因としては、この時の俺のレベルに対して教科書のレベルが高すぎたということと統計検定2級に合格するという目的にはあまりマッチしていない教科書だった。2級で求められる内容以上の知識も載っていたため、逆に混乱してしまった。
結局、理解を深めるために、ネットで情報を得ることにした。
とけたろうさんのYouTube・ブログを発見
ネットでいろいろ情報を集めている中で、とけたろうさんのYouTubeを発見した。一応、とけたろうさんのYouTubeは知ってはいたが、視聴まではしていなかった。試しに見てみると、とてもわかりやすく、内容も2級にマッチしていた。
今の俺に必要なのはこれだと思い、理解が乏しい分野の動画を視聴し、その後該当分野の過去問テキストを解いてみるやり方に変えてみた。依然として解けない問題はあるものの、解説の理解度やなぜこの計算式になるのかなどが以前よりわかるようになってきたのである。ひとまず、このやり方で分野別に解き直しを行い、その後通しで再度解き直しを行い、さらにとけたろうさんのブログの練習問題も一通り解いた。

仮説検定の計算式で大混乱
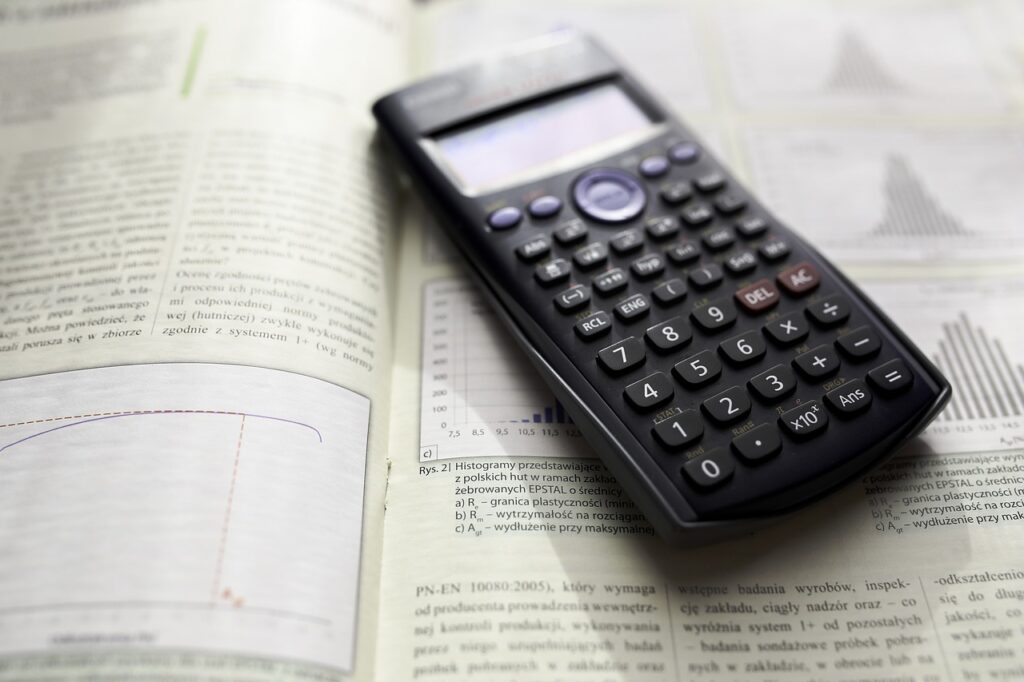
とけたろうさんのYouTube・ブログにも助けられながら、一通りの知識はインプットできた。しかし、アウトプットで大きな混乱が生じた。
統計検定2級には仮説検定という分野がある。ざっくりだが「ある仮説が正しいかどうかを検証する」みたいなものだ。この仮説検定には母分散に関する検定や母平均に関する検定、適合度の検定などいろんな種類がある。それぞれで使う式などが変わってくるのだが、この時に大きな混乱が生じた。どの時にどの式を使うのかが、なかなか慣れず、問題を解く時に判断・立式に時間がかかってしまっていた。
実際に試験の時も、ここの分野の問題に多くの時間を使ってしまったと思うし、得点率も低かった。実際に統計検定の勉強をしてみて、ここら辺の分野は多くの人がつまづきそうな範囲だなと感じたので、これから勉強する人は注意してほしい。
実際の試験はどんな感じか?
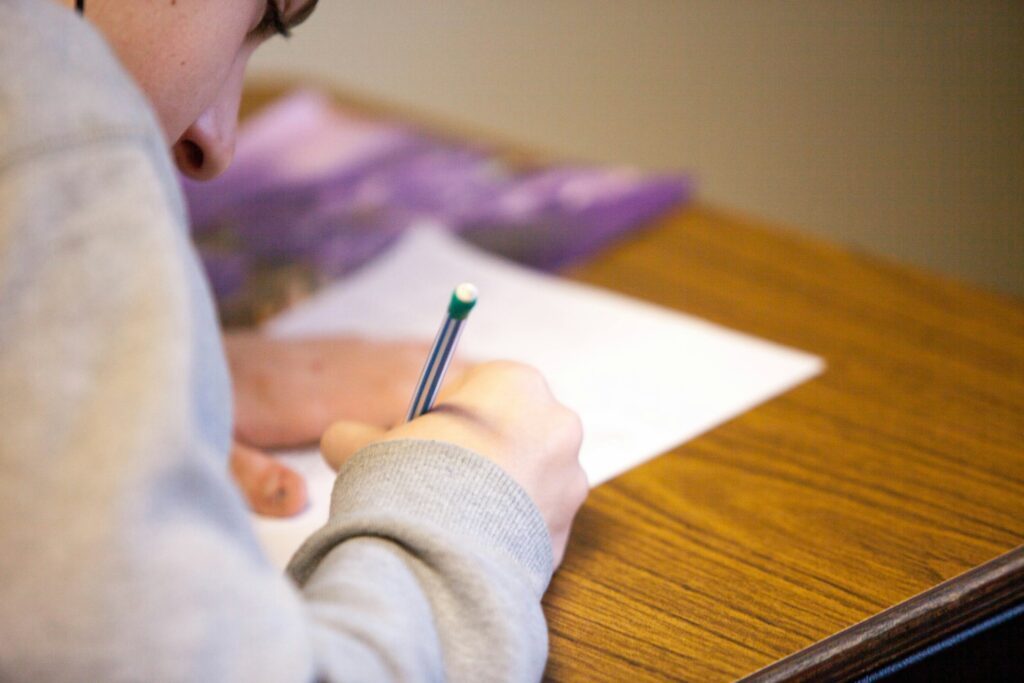
実際の試験はCBT方式といって、コンピューター上で問題を解くことになる。規定でどんな問題が出たのかなどは公表してはいけないことになっているので、問題の詳細は教えられない。
試験の感想としては、まず時間が足りなかった。試験時間は90分で問題数は35問程度であり、単純計算で1問に対して3分もかけることができない。計算があまり必要のない問題を素早く処理し、計算が必要な問題に時間を使えるようにする必要があると思った。また、やはり立式に時間をかけているようじゃ無理。
先ほどの仮説検定の計算式などでどの計算式を使えばいいかを悠長に悩んでいては、時間が足りなくなる。立式は素早くできるようにしなければならないと感じた。
俺は最後の方の問題はとりあえずテキトーに答えを入力だけして終わってしまった。それらの問題がどれほど正解になっていたかはわからない。
あとは、電卓に慣れておくことも一つ大事だと思った。今は普段電卓を使う時は、スマホの電卓で計算する人がほとんどだと思う。しかし、当然だが試験中にスマホは使えない。普段の統計検定の勉強の段階から、試験に持ち込む電卓を使用すべき。
問題を解き終えたら、その場で合否が出るようになっている。試験会場の人にも合否を確認されるので、落ちてたらめちゃくちゃ恥ずかしいと思う。俺も正直手応え的に自信がなかったから、めちゃくちゃ心配だったが、無事に合格できた。
結論
やるべきことは以下だ。
- 過去問テキスト(演習量を増やすなら複数やった方がいい)をまずは解いてみる。
- 過去問の解説はネイピアDSさんのnoteを参照する。
- わからなかった知識や新しい知識は問題を時ながら、とけたろうさんのYouTube・ブログでインプット。
- 問題を解き直して、アウトプットできるようにしていく。
これの繰り返しだ。
俺の経験からは教科書はなくてもいい。とけたろうさんのブログで全然足りる。
俺の学習期間は過去問を購入したのは7月くらいだった気がするので、そこから考えると10ヶ月くらいかけているが、3月くらいまではダラダラやっており、3月から本腰を入れ始めた。実質学習期間は3-4ヶ月だと思われる。
なので、俺と前提の学力が同じくらいの人はこの学習期間で合格可能だと思う。もちろん、どれくらいの勉強時間なのかにもよる。
統計検定2級の合格率は50%くらいと言われている。半分は落ちる試験なので、油断しない方が良い。俺も正直ギリギリで受かっているので、偉そうなことは言えない立場である。
統計検定合格を目指している人はぜひがんばってほしい。